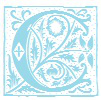 二章:霧中の橋
二章:霧中の橋
象牙の塔の周辺が晴れ渡る事はない。
切り立つ崖に囲まれたその姿は、沖合から見ればぼんやりとした姿が見えはするものの、その全容
はいつも霧に囲まれているのだ。故に、その姿を完全に知る者は本土にはおらず、象牙の塔に住まう
魔術師達も、象牙の塔から本土の様子を窺う事は出来ない。
恐らくそれも、象牙の塔を護る魔法の一つなのだろう。
光の帝国から流れた魔術師の群れである塔は、メイソンが口にしたように帝国にとっては苦々しい
存在でしかないだろう。所謂魔法を使える存在は、世界には数多くあれど、自ら魔法の媒体となる魔
石を生みだせるのは、帝国出身者しかいない。
帝国は、一枚岩である事を望んでいる、と誰かから聞いた。それはアルンハイムから流れた両親か
らだったかもしれないし、或いは旅芸人の噂話で聞いたのかもしれない。もしもそれが本当であった
なら、やはり象牙の塔は帝国にとっては許されざる存在で、いつ攻撃を仕掛けてきてもおかしくない
のだ。
だからこそ、象牙の塔はゴルゴンダ国に属し、その軍隊を駐留させている。そして、自衛の一環と
して霧の魔法で身を隠す事も有り得るのかもしれない。
しかし、常に霧に囲われているというのは、決して気持ちの良いものではない。
ましてや、旅立ちの日に。
ゼイクは塔の入り口で、真っ白な空を見上げて呻いた。
結局、ゼイクはこの試験を断る事が出来なかったのだ。きっと、断っても良かったのかもしれない。
だが、試験はやはり二人一組であるし、もう一人の旅立ち人であるラシルは大変乗り気だった。ゼイ
クがもしも断れば、末代まで祟りそうなほど。
きっと、ラシルは二十三年前の戦いに参加し、そして今の今まで眠りに落ちていたクローアを見て、
完全に火が着いてしまったのだろう。
メイソンも同じくあの戦いの指揮官ではあったが、けれどもそこまで、凄みのようなものを感じな
いのだ。メイソンの魔術師としての腕は紛れもなく超一流なのだが、彼の特化した能力――千里眼と
いうものが、確かに凄いのだが地味だからだろうか。
それに対して、クローアの幻視は自分達が被検体となったからだろう、はっきりと凄いと分かるの
だ。鱗一枚一枚まで明確に再現成された竜の幻覚。見た者全て夢現の境が判別できず、最終的には狂
気に陥るという理由が、身を以て思い知らされた。
何よりも、その姿は二十三年間の間何一つ変わっていないのだ。
それは彼女の眠り――むしろ封印の所為だろう。時さえ止める封印により、クローアは二十三年前
そのままの姿で現れたのだ。それは、魔術師というものに心底憧れている者にしてみれば、どうしよ
うもなく心惹かれるものなのだろう。
ゼイクには全く分からないが。
だが、ゼイクは全く心動かされなかったにも拘わらず、こうして旅立つ事を余儀なくされている。
それには、ゼイクが結局自分で自分の進退を決めなかった所為にあるのだろう。
魔術師試験だって、よくよく考えれば上級試験を受けるのを最初から止めていれば良かったのだ。
だらだらと、落ちたら田舎に引っ込もうなどと考えずに、試験の前に塔を退席していれば良かったの
だ。それをしなかったから、こんな事になっている。
そして今も、結局は自分の進退をラシルに任せてしまっている。
優柔不断にもほどがある。
げっそりと溜め息を白い空の下に向けて吐き出し、ゼイクは冷たい壁に寄り掛かった。まだ誰も来
ていない。どれだけ溜め息を吐き出そうとも、誰にも聞こえていないと思った。
「あら、溜め息なんか吐いちゃって。最近、いつもそうね。」
踊るような声音に、ゼイクははっとした。
この白い霧の中には相応しくない日に焼けた肌を見せたのは、ジェザシータだった。いつもは重苦
しい金属の鎧を纏っているのに、今日はハードレザーの胸当てと、薄い鉄の鎖で編み込んだ腰当に幅
広の剣を差し込んでいる。
ジェザシータの見慣れぬ軽装に、ゼイクはもしかしてと思う。
「ジェザシータ。もしかして、俺達と一緒にゴルゴンダに行く軍人っていうのはジェザシータなのか?」
すると、彼女は屈託なく笑った。
「ええ、そうよ。」
「尤も、彼女だけではないがな。」
ジェザシータの柔和な声を断ち切るように、まるで鉄のような厳めしい声が振り下ろされる。全て
を跳ね除ける声と共にジェザシータの背後から現れた人影は、正に鋼鉄を思わせるような巨躯の持ち
主だった。そしてその姿を見た瞬間、ゼイクは自分の顔が強張ったのが分かった。
ジェザシータと同じく軽装ではあるが、革の胸当てにここぞとばかりに押された烙印は、紛れもな
くゴルゴンダ国軍の紋章であり、それを大々的に見せつける男は、ゼイクの知る限り一人しかいない。
ゴルゴンダ軍が象牙の塔の守護者であると同時に、監視者であるのは誰もが知っている事ではある
が、それをはっきりと誇示する男。
ズウェイン・ゴルダー。
ジェザシータのような柔らかい物腰も、友好的な態度も示さない。むしろその真逆――威圧的で見
下すような態度を取る事が多い、ゴルゴンダ国の下士官だ。
まさかこの男が、今回の旅に同行するのか。
ゼイクはズウェインの出で立ち――革の胸当てをして背に大剣を背負った姿をまじまじと見て、自
分の後悔が最終局面に達した事を悟った。そして、もはや逃げ場はない事も。
もしかしたら蒼褪めてさえいるかもしれないゼイクを、ズウェインは鼻先で嗤う。ただし、眼は全
く笑っていない。
「『偽りの鏡』の所有者をゴルゴンダに届けるからどんな大役かと思えば……。同行者は半人前の魔
術師か。全く、メイソンは何を考えているのか。」
心底呆れたような口調を滲ませたズウェインに、ジェザシータが嗜めるようにその名を呼んだ。
が、正直なところゼイクは、ジェザシータの気遣いは全く無用であるとしか言えない。実際のとこ
ろ、ゼイク本人も自分が半人前でしかない事は理解しているし、メイソンが何を考えているのかと不
安にも思っている。だからズウェインの嘲るような言葉は、まるごとゼイクの本心でもあった。
ゼイクが黙っていると、ズウェインの嘲る口元は、ますます深く歪められる。ズウェインは、ゼイ
クが半人前――いや、むしろ半人前以下でしかない事を重々承知していながら、そしてゼイク自身も
それを否定できないと知っていながら、わざわざゼイクを貶めるような言葉を吐いているのだ。
嗜虐主義者め―――。
象牙の塔の学徒達が、常々ズウェインに対して吐き捨てている台詞を、ゼイクは腹の中で呟く。ゼ
イクの心中を知っているであろうズウェインは、更に言い募る。
「まったく。せめてウェスペルあたりの学徒を連れていけたなら、良かったんだが――。」
「そんな事、二度と言わせないわ。」
ズウェインの台詞を遮ったのは、甲高い娘の声だ。そして、ゼイクがこんな旅に出る破目になった
あの日から、よくよく聞くようになった声でもある。
「ウェスペル・グラキエースよりも、この私のほうがずっと優れた魔術師である事を、この度で証明
してみせるわ。」
好戦的な表情を貼り付けたラシルは、恐れもせず、学徒の天敵であるズウェインの前に立ちはだか
った。尤も、小娘が目の前で仁王立ちしてみせたところで、軍人の口が閉じるわけがない。
「旅をするにあたり重要なのは、魔術師である事ではない。野盗や魔物を追い払えるだけの力だ。実
戦経験もない上に、剣一つ碌に使えぬ半人前が、ウェスペル・グラキエースよりも優れているとは、
笑わせる。そもそも、お前はウェスペルほどの評価を今までに一度でもされた事があったか?」
ズウェインの言葉に、ラシルは言葉に詰まる。
ウェスペル・グラキエースは、象牙の塔の学徒の一人だ。ゼイクやラシルよりも四つ上の学年にな
るが、ゼイクも名前くらいは知っている程度には、有名人だ。灰白の長い髪と、魔術師とは思えない
ほど恵まれた体躯を持つ男子学生は、けれども、何をして有名であるか、はよく分からない。ただた
だ、教員達からの評価は専ら良いのだ。
ズウェインは、もしかしたらウェスペルが何故評価が高いのかを知っているのかもしれない。それ
は、たった今ズウェインが口にした、実戦に由来するものであるのかもしれない。
ラシルは確かに優秀だが、しかしそれ以上でもそれ以下でもない、魔術師としては優秀だが、けれ
ども魔術で何かを成し得た事はない。学生の身分である事を考えればそれは当然なのだが。
黙り込んだラシルに、嗜虐的な笑みを浮かべるズウェイン。
同僚の悪癖を止めようと、ジェザシータがとうとう口を開いた時、それよりも早く、玲瓏な声が冷
たくその場を打った。
「年端もいかない子供を嬲るような軍人を、私の護衛にするのか?」
冷ややかな声で問いかけながらラシルとズウェインの間に割って入ったのは、今から自分達が護る
べき存在――偉大なる魔女クローアだった。真っ白な髪を揺らして肩越しに問う魔女に、後からやっ
て来たメイソンが、のっそりと答える。
「ズウェインは優秀な軍人だ。その子達に足りぬところを、十分に見抜いている。」
「それを知っている上で、口で嬲る事に、何の関係がある?」
クローアは黒い眼でズウェインを見上げた。幻視の眼で見つめられ、ズウェインも流石にたじろい
だ。幻でも見せられては敵わないと思ったのか、慌てて眼を逸らしている。
「そもそも、私には護衛は不要だ。確かに、二十年近い眠りで多少の不便はあるが、それでもこの場
にいる誰よりも魔術に精通し、役に立つだろうと自負している。つまり――。」
クローアの眼が、ラシル、ゼイク、ジェザシータと順繰りに見やり、再びズウェインをひたりと見
据える。
「君が護衛する相手は、私ではなく、この二人の学徒だ。それに対してその口の利き方は、どうかと
思うがね。」
最後に一つ、鋭い視線をくれてやると、クローアはズウェインの事はどうでも良いのか、興味を失
ったように眼を離した。ズウェインはといえば、顔を真っ赤にして、ようやくクローアを睨み付けて
いる。
「クローア、君は少し言葉が過ぎるぞ。」
メイソンが、クローアの態度を嗜め、しかし、とズウェインにも釘を刺す。
「君も、もう少し学徒に対する言葉を考えてもらいたい。君は、ヘーゲルから借り受けた軍人だ。些
細な言葉の行き違いで、彼からの好意を無碍にしたくはないのだよ。」
それは、聞きようによっては、ゴルゴンダとの関係を悪化させたくないというふうに取れるし、実
際にそうなのだろう。ゴルゴンダの庇護なくしては、象牙の塔は光の帝国によって捻り潰されてしま
う。だから、メイソンはゴルゴンダ軍人が象牙の塔で大きな顔をしているのを、黙って見ているのだ
し、ズウェインの悪辣な言葉で学徒が傷ついているのも、聞き流しているのだ。
今回口を挟んだのは――口を挟めたのは、クローアがいるからだろう。
ゼイクには政治は分からないが、クローアがメイソンにも、ゴルゴンダの大統領であるヘーゲル
にも、そして世論にも、大きな影響を与えるであろう事は分かる。
幻視者である偉大なる魔女。
二十三年前の戦禍において、優れた功績を挙げた者の中に、必ずクローアの名前は上がる。そんな
彼女が目覚め、ゴルゴンダ軍人の態度に眉を顰めたことで、ゴルゴンダへの諫言を口にしやすくなっ
た事は確かだ。
ゴルゴンダに今まで首根っこを掴まれていたメイソンは、ゼイクとラシルに向き直り、学長らしい
顔で二人に餞の言葉を紡ぐ。
「さて、ラシル、ゼイク。二人にはこれからゴルゴンダに向かって貰う。クローアとゴルゴンダ軍人
がいる以上、危険はない。だが、それは決して絶対ではない。不測の事態というのは、いつでもどこ
でも起こるものだ。それに対して、如何に対処するのか――それを持って、君達二人の試験の合格と
しよう。」
慎重に。されど果敢に。汝ら決して点に囚われる事なかれ。
メイソンは、象牙の塔の学是を低く伝える。
「さあ、行きたまえ。世界の血が君達の血と共にあらん事を。」
三重に閉ざされていた象牙の扉の門が、音もなく開かれる。強い風と共に潮騒が流れ込み、髪を煽
り立てた。その向こう側に、真っ直ぐと海峡を渡る橋が伸び、海と空の間に、靄がかった深い緑色の
大陸が見えた。
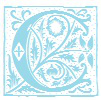 二章:霧中の橋
二章:霧中の橋