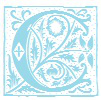 序章:同化の破片
序章:同化の破片
周囲は火の海と化していた。
いや、もしかしたら肌を焼く炎さえも実在するものではないのかもしれない。
魔術師達を率いるメイソン・アーガスは身体の周りを翻って走り回る炎の尾を見ながら、苦々しく
思った。現実と虚像の区別が分からぬ若い魔術師達は、混乱し、中には既に心を砕かれてしまった者
もいるようだった。メイソンとて、何が虚構であるのか分からぬのは同じ事。いつ、彼らと同じよう
に狂気に走るか分からない。
魔術師として名を馳せたメイソンでさえ、まさか『偽りの鏡』の威力がこれほどまでとは思わなか
ったのだ。そして、『偽りの鏡』がよもや白の集団の手に渡っていたとは。
炎の勢いは、まるで衰える様子がなかった。
世界を混沌に陥れた白の集団は、連合軍を前にじりじりと後退している。だが、その手には神具が
幾つか渡っていたのだ。そうした噂は以前からちらほらと聞いていたが、本当だったとは。そしてそ
の威力がこれほどとは。
しかし、メイソンを始めとする連合軍の指揮官を責める事は誰にも出来ない。何せ、神具――この
世界を創造したという『世界の血』が最初の人に与えたと謳われる道具は、伝承上『世界の血』を尤
も濃く受け継いでいると言われている光の帝国の皇帝でさえ、全ては見た事がないのだ。
今回の戦いで、帝国が管理している神具の幾つかを、初めて見る機会が得られたものの、残りのも
のは何処にあるかさえも分からない。ましてその効果を知る者は、ほとんどいないのだ。メイソンは
帝国に管理されている神具を実際に見る事が出来た為、その存在を知っているが、普通の人々は存在
すら信じていないかもしれない。
だが、今、白の集団の魔術師達によって高く掲げられた『偽りの鏡』が青々と輝き、メイソン達を
明るく照らし出している。一体何処で、彼らがそれを見つけ出したのか、そんな事は今はどうでも良
い。今一番問題なのは、『偽りの鏡』の蒼褪めた輝きが、間違いなくメイソン達に向けられていると
いう事だ。
『偽りの鏡』から発せられる灯りが生み出すものは、悉くが幻だ。
限りなく本物に近い、幻。
故に、それの区別の仕方など、分かるはずもない。
身を焦がす炎を幻だと侮れば、気がついた時には現実の炎に巻き込まれているだろう。しかし本物
だと思えば、その場でたたらを踏むしかない。
勿論、メイソンとて手を拱いているわけではない。荒れ狂う炎に向けて、部屋全体を覆い尽くす冷
気を掲げた杖の先から放っている。だが、それらは全て炎の飲まれてしまうのだ。それも炎を呼び出
す白の集団の魔術師の力が、メイソンの凍れる力よりも勝っているからないのか、それとも幻だから
なのか、全く見当がつかない。
このままいけば、メイソン達は幻とも現実ともつかない炎に嬲り殺しにされるだけだろう。そして
メイソンの一画を倒せば、今まさに全世界の力を以てして封じ込めようとしている白の集団による混
沌が、メイソンの屍を越えて再び噴き上げるだろう。
だから、メイソンは一歩も退く事は出来ないのだ。逃げる事も、そして負ける事も出来ない。
弟子達が『偽りの鏡』の見せる幻視によって一人、また一人と恐慌を起こす中、それを助ける事も
出来ず、メイソンは必死になって突破口を探していた。
じり、と汗が額を伝い、眼に入る。視界が歪んだ。真と偽を見極めようとしていた視界が閉ざされ
る。それ以上に、その隙は白の集団にとってはメイソンを攻撃するまたとない好機に見えただろう。
魔術師としての評価は間違いなくメイソンのほうが上である為、例え『偽りの鏡』で足止め出来たと
しても、首級を上げるには至らない。
だからこそ、メイソンの視界が一瞬とはいえ塞がれた今こそ、好機であったのだ。
『偽りの鏡』の周りで詠唱していた魔術師達の視線が、貪欲に歪んでメイソンを射抜く。掲げた杖
の行く先は、むろん、メイソンの額だ。今や杖の先には、凶暴な輝きが灯り、発射される時を待って
いる。
振り上げられる輝き。
同時に聞こえたのは、木々を薙ぎ倒すような強風が、空を切る轟音。
そして湧き上がる悲鳴。
だが、その悲鳴はメイソンのものではなかったし、悲鳴が上がる前にはっきりと、硝子のようなも
のが砕ける音がした。その時にはメイソンは視界を覆っていた汗を拭い去り、今しがた自分の頭上を
駆けていった風を追いかけて、杖を振り上げている。
杖を振り上げるメイソンが見たものは、駆け抜けていった風の残像のような黒髪。黒髪の中心から
砕けていく『偽りの鏡』の破片。それを見て悲鳴を上げる白の集団の魔術師達。そして、鏡が砕けた
事で同様する魔術師達に向けて放った、自分の冷気だった。
床を這うように伸び、そして突き上がった冷気は、一瞬にして魔術師達を氷の彫像へと変貌させた。
その瞬間、身体を焦がしていた炎が消え失せる。
残ったのは、心を砕かれた弟子達と、メイソン、そして鏡の中心に刃を突き立てた風だけだ。
「クローア……。」
炎で焼かれた喉も、実際は全くの無傷だった。しかし喉の奥には痛みが残っているような気がして、
メイソンは何度も唾を飲み込み、それから名前を呼んだ。
「よく、壊せたな……あれを。」
砕けた鏡の破片を極力見ないようにしながら――砕けていても魔力が残っている可能性はある――
呟くと、若い女の、しかし酷く落ち着いた声が聞こえた。
「魔法はどうせ跳ね返されるだろうと思っていた。壊すなら、物理的に壊すしかない、と。そしてあ
れが幻視なら、まずは幻視される隙を与えなければ良い。何が発端となるか分からなかったから、眼
を閉じ、耳を塞いだ。」
女は耳栓を取り、人差し指に青い石のついた指輪を嵌めた手で握っていた短刀を床に落とす。カラ
ン、と短刀が乾いた音を立てている間に、ゆっくりと身を翻してメイソンのほうを振り返った。そ
の姿を見て、メイソンは絶句した。
「……クローア!」
「……ああ、やられた。」
クローアの声は淡々としていたが、彼女の顔は左眼から流される血によって覆われていた。そして、
左眼には深々と鏡の破片が突き刺さっていた。だが、それは少しずつ小さくなっているようだった。
まるで、クローアの眼に吸い込まれていくかのように。
「同化しているぞ……!」
「そのようだな……。どういう仕業かは、全く分からないが……。」
しかし、そんな事を言っている暇はないと言わんばかりに、クローアは首を一振りする。
「白の集団はアルゴンヌ海に集結している。皇帝と教皇は既にそっちに向かっている。ヘンリーはも
う布陣しているようだ。私達も行かなくては。」
幸いにして、鏡の破片と同化している眼からは、もう血は流れていない。しかし、とメイソンは思
った。だが、すぐにそんな事を言っている暇ではないと考え直す。
革命と称して各地で粛清という名の殺戮を繰り返し、世界を震撼させた白の集団と、その頭領であ
るアンブロワーズ。彼らに対抗する為、有史以降常に小競り合いを続けている光の帝国と軍事国家で
あるゴルゴンダ、そして被差別民族である海人、川人、巨人達が連合を組んだのだ。
その結果、白の集団はまさに追い詰められようとしている。
この機会の逃してはならないのだ。
しかし、そう思ったメイソンの視界に、クローアの髪が映り、彼は再び声を上げた。
「クローア!髪が!」
長く黒いクローアの髪。それは、今、目の前で白く変わりゆこうとしている。それも、神具を同化
してしまったからだろうか。
だが、その疑問をクローアは一蹴した。
「急ぐぞ、メイソン。話は、この戦争が終わってからだ。」
それから半年後、アルゴンヌの海戦は連合軍の勝利によって幕を閉じた。
アンブロワーズは息の根を絶たれ、しかし万が一の事を考えて、白の集団が処刑、または自決した
場所は厳重に封印された。封印は六つの鍵がかけられ、そして更に四つの鍵が施され、最後に再び四
つの鍵によって閉ざされた。
そして、世界は再び小競り合いの続く喧噪へと戻って行った。
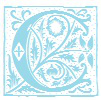 序章:同化の破片
序章:同化の破片