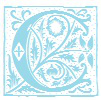
どちらかと言えば低めの、すっと良く通る女の声が響いた途端、部屋の中は完全に光に満たされた。
はっとしたゼイクとラシルが蠢いて口を開いた壁を見れば、そこには蒼褪めたローブを纏った女が、
ひっそりと立って二人を見ていた。
歳の頃はゼイクやラシルよりも上だろう。具体的な年齢を言い当てる事は出来なかったが、けれど
も歳を経ているようには見えない。まだ、若い。
白い髪は床に届くほど長く、それを今にも解けそうな緩やかな三つ編みにして流している。
ゼイクとラシルを睥睨する瞳も黒く、ただしそれは一つしかない。もう片方の瞳は黒い眼帯で覆わ
れて見えないのだ。
「それで?襲撃者には見えないから、迷い込んできた学生といったところか?それにしては、随分と
乱暴だと思うけれど。」
「あ、貴方は……?」
ようやく声を発する事が出来たのはラシルだった。
「此処は象牙の塔の地下回廊。普通の人間が入れるわけはないわ。なら、貴方はこの塔の関係者?メ
イソン学長の事を知っているようだし、貴方がこの試験の教官?」
そんなはずがないだろう、とゼイクはラシルの台詞に突っ込んだ。現れた女は、どう考えてもゼイ
クとラシルの事を初めて見た様子だった。ならば、試験の事も知らないに違いない。
白い髪を揺らした女も、ゼイクと同じ事を考えたのだろうか。口元に、本当にあるかないかの微苦
笑を湛え、ゆったりと口を開いた。
「私は此処の教官になった記憶はないな……メイソンが勝手に籍を入れていなければ。この塔の関係
者かというのも少し違う。ただ、この塔の設立者であるメイソンとは知り合いではあるが。あと、こ
の塔の地下は確かに解放されていないけれど、例えば封じる前に入れば、普通の人間でも入るには事
足りる。」
女は最後に謎めいた言葉を付け加えて、それで、と髪とは対照的な黒い眼で、ゼイクとラシルを交
互に見やった。
「私の質問にも答えて貰いたいんだが。とりあえず、お前達がこの塔の学徒であり、そしてメイソン
は未だに此処にいる事は分かった。そして、試験の名目でこの場所にやって来た事も。だが、試験は
何故、この場所で行われている?」
「……そんなの、知らないわ。」
当たり前だ。しがない学徒に、試験の場所が何故この場所なのかなど、知る権利は与えられていな
い。試験の内容でさえ分からなかったのに。
そこまで思って、ゼイクははっとした。そういえば、試験はどうなるのか。とりあえず竜は消えて
しまったが、あれで合格なのだろうか。しかし、目の前に現れたこの女は、明らかに口ぶりからして
試験とは全く違う話だ。この場合、一体どうなるのか。
うろたえ始めたゼイクは、救いを求めるようにラシルを見るが、ラシルもどうにか努めて冷静を装
っているが、この事態にはついていけないようだった。
そんな低級魔術師二人を見てどう思ったのか、女は小さく溜め息を吐くと、虚空に向かって叫んだ。
「メイソン!どうせ視ているんだろう!それともこの二人が此処で何を為すのか見届けないほど、耄
碌したか?」
鋭い声に、まさか空間が切り裂かれたわけではあるまい。
だが、女の声が強く弾けるその刹那、薄暗い地下回廊だったその場所は、暖かな光が灯り赤い絨毯
が敷かれたものへと変貌した。古びているが豪奢な机が置かれ、雑然と本が積み上げられた中央に位
置しているのは、ゼイクも見た事があるこの塔の設立者、メイソン・アーガスだった。どういう仕業
か――いや、魔法である事は分かっている――メイソンの部屋へと移動したらしい。
しかし、唐突に現れた三人に、メイソンは顔色一つ変えなかった。むしろ、いきなり設立者の部屋
に放り込まれたゼイクとラシルのほうが、唖然としてしまっている。いや、もう唖然としすぎて何が
何だかわからない。
だが、どうやらこの事態を引き起こしたのであろう女は、メイソンと同じく表情を微動だにせずに、
メイソンを見据えている。
「これはどういう事だ、メイソン?何故、あの部屋に学徒がいる?」
静かに、だが威圧的にメイソンに向かう女に、メイソンは小さく溜め息を吐いた。
「久しぶりに会う友人に対する第一声がそれかね、クローア?確かに君にとって、この年月は夢の一
瞬なのかもしれないが。」
「ああそうだな、メイソン。久しぶり。それでどういう事だ?私が眠る部屋で試験をするなんて、気
でも狂ったか?」
女の声は、冷やかさを帯びた。一切の妥協を許さぬ声に、メイソンはもう一度溜め息を吐いた。
「まさか、気が狂ってなどいない。ただ、あの部屋は低級から上級に行く者を見定めるには、ちょう
ど良い場所だ。」
そうして、メイソンはようやくゼイクとラシルに視線を巡らせた。ほんの一瞬の事だったが。思わ
せぶりな視線を、二人の低級魔術師に巡らせると、彼は直ぐに女に目線を戻してしまう。
「君が眠る部屋は、現実と幻が混じる場所。その場所ほど、魔術師の力を試すに相応しい場所はない。
ああ、勿論分かっている。幻と対峙した時の危険性は。」
「幻?」
メイソンの言葉に、声を上げてしまったのはゼイクだけではない。ラシルも同じだった。あの部屋
で見てきたもの――あの炎を噴き上げる竜は、幻だったというのだろうか。肌に当たる炎の熱さも感
じたというのに。
しかし、戸惑いをいち早く脱ぎ捨てたのは、ラシルだった。
「幻?クローア?もしかして、二十三年前のアルゴンヌ海戦で、幻視により白の集団を破ったという、
あの幻視者クローア?」
ラシルの高い声に、クローアと呼ばれた女は首を竦め、メイソンは静かに頷いた。ゼイクは、話に
ついていけずに黙って立ち尽くすだけだった。
勿論、クローアの名前は聞いている。
幻視者クローア。
白の集団が強奪した幻視鏡『偽りの鏡』を破壊する際に、その眼を砕いた鏡の破片で傷つけてしま
ったが故に、幻視の力を持つようになったと言われている。そしてアルゴンヌ海の戦いにおいて、最
後の封印を仕掛けた後、魔力を使い果たして眠りに落ちたと、本には書いてあったのだが。
それが、目の前にいる女であるとは、俄かには信じがたかった。何せ白の集団との戦争は二十三年
も前、ゼイクが生まれる前の話だ。その時、最前線で戦った者は、メイソンを始め、皆が良い歳にな
っている。だが、クローアと呼ばれた女は、それほどまで老いてはいない。ゼイクほど若くはないが、
メイソンのように初老の域に差し掛かっているわけではなさそうだった。
だが、ゼイクの疑問を無視して、メイソンはラシルの知識を褒める。
「その通りだ、流石はラシル。良く知っていたな。」
「そんな……偶々、本で読んで知っていただけです。」
メイソンの賞賛の言葉に、そばかすだらけの頬を染めるラシル。そのままの勢いで、クローアにつ
いての質問を続けようと口を開いている。
だが、それはクローア本人によって閉ざされてしまった。
「私の事など知っていても、何も偉い事などはないな。それよりも、私は、幻視による危険性を知っ
ていながら、何故、学徒を私の部屋に送り込んだのかを知りたい。私が壁に囲まれて眠っているから、
幻視もさほど大したものは出てこないだろうと考えていたのか?いや、それよりも何故、幻視が起き
た時点で、危険だと見做さなかった。」
クローアの黒い瞳が、きゅっと吊り上り鋭くなる。しかし、糾弾されるメイソンは、悲しげに首を
振るだけだった。
「恐ろしい事を言うね、クローア。幻視が現れたから危険だと見做さなかったのか、とは。では危険
だと見做して、それで私はどうすれば良かったのかね?友を、よもやこの手で始末せよとでも言うの
かね?戦いで傷つき、深い眠りに落ちた君を?」
「少なくとも、学徒を近づけるべきではなかった。」
メイソンの言葉に、しかしクローアは、白い髪を揺らして言い募った。だが、それに対してのメイ
ソンの言葉はあっさりしたものだった。
「安心したまえ……あの場所は常に私の監視下に置かれているよ。学徒が入る時は、私が必ず視てい
る。」
「なるほど。千里眼メイソンの力は衰えていないという事か。」
「まあ、寄る歳には勝てないがね……。それに、君が目覚める事も流石に予想はしていなかった。私
にも、そればかりは謎だ。」
けれども、それはクローアにとってはさほど驚くべき事ではなかったらしい。どうして目覚めたの
か、既に彼女は分かっているようだった。ただし彼女の一つだけの眼は、何故かはっきりとゼイクを
見たまま、目覚めた理由を告げた。
「……私の夢の鍵が抉じ開けられた。だから、無理やり目覚めさせられた。それだけだ。」
「何……?!」
クローアの台詞に、メイソンが初めて焦ったような色を浮かべた。思わず、といったふうに身を乗
りだしている。
だが、それには流石にゼイクも反応した。夢の鍵は、白の集団をアルゴンヌ海に封じた、封印の鍵
だ。全部で十四あるというそれは、白の集団と戦った時の指揮官十四人がそれぞれ持っていると言わ
れている。そしてそのうちの一つが、今回の試験で問題となった鍵だ。
その鍵が、外れた、というのは。
身を乗り出した魔術師達に、クローアは顔を顰めた。そして、ゼイクから視線を外すと、メイソン
を叱りつけた。
「お前の所為だろう、メイソン!私の鍵に親和性のある魔力を注げば、鍵が解ける事くらいは分かっ
ていたはずだ。」
あの、稲妻。
苦々しげに放たれた瞬間、ゼイクはクローアが何故こちらを見ているのか理解した。あの時、稲妻
を放ったのは、紛れもなくゼイクだったのだ。
「そんな………。」
ゼイクを見て、微かな非難を混じらせた声を放ったのは、案の定ラシルだ。よくよく見れば、メイ
ソンも非難しているような気がする。
だが、それを打ち砕いたのは、やはりクローアだった。
「これは、夢の鍵の特殊性を知っていながら、私と夢の鍵の眠る部屋で魔法試験を続けたメイソンの
咎だ。稲妻を放った者には何の責任もない。それに、確かに私の持つ鍵は解かれてしまったが、まだ
九つの鍵が残っている。狼狽えるにはまだ早い。」
「だが、他の者はそうは思わないだろう。」
メイソンは、ゆっくりと、クローアの台詞を否定するように、首を横に振った。
「君が眠っている二十三年間、様々な事が変わった。帝国は帝位が変わり我々への弾圧を強め始め、
ゴルゴンダとの紛争も再び起こり始めている。もう、あの時のような一枚岩ではないのだよ。」
世界は不安定化している。
それは、象牙の塔にいても思う事だ。白の集団がいた時は、明らかな戦火が飛び交っていたが、し
かしあの時の敵は、全ての種族の敵だった。帝国も、魔術師も、海人も巨人も魚人も、皆が味方であ
ったのだ。だが、共通の敵が消えた今、あの時のような同盟は望めない。
「それに、アルンハイム公が暗殺された。」
「何?」
この時、はっきりとクローアの声に、ひび割れたような動揺が走った。一つしかない黒の眼を大き
く見開き、メイソンを信じられない物でも見るかのような眼で見ている。
アルンハイム公は、ゴルゴンダ国と光の帝国を分かつアルンハイム山脈麓一帯を領地とする、光の
帝国の大諸侯だ。勿論、アルゴンヌ海戦にも参加しており、やはり夢の鍵の一つの所有者であった。
しかし、十八年前、何者かによって暗殺され、領地は荒廃、今や山脈越えは山脈そのものの険しさと、
アルンハイム領地の治安の悪さにより、困難を極めるものとなっている。
そして、アルンハイム公が暗殺された今、彼が手にしていた夢の鍵も、行方不明となっているのだ。
「君が眠りに落ちて、僅か五年の事だ。もはや、我々はあの時のようには振る舞えない。」
「……それで?だから、お前はどうしているんだ?こうやって象牙の塔に、魔法使いの卵を集めて温
めて、何をしている?アルンハイム公――ヘンリーが殺されたというのに。」
クローアは何処か嘲るような、辛辣な口調で言い放った。その台詞に対して、メイソンはやはり悲
しそうに首を振った。
「私に出来る事は、光の帝国に属さない魔法使い達を集めて、守る事くらいだ。光の帝国は魔法使い
達を徴兵しているが、光の帝国以外の国の魔法使いは、それは酷い扱いを受けるそうだからね。特に、
魔石を持たない者達はね。」
光の帝国で人間扱いされるのは、魔石を持つ人種だけだ。それ以外の、魔石を持たずして魔法を使
う人種は、奴隷として扱われる。人種による階級制度が余りにも厳し過ぎる国なのだ。
「だが、それを光の帝国が黙って見ているわけではないだろう。お前は何か取引でもしたんじゃない
のか?」
「そんな事はしていない。私は、ゴルゴンダ軍に助けを求めただけだ。」
光の帝国と現在敵対関係にあるゴルゴンダには、魔法を使える人種がほとんどいない。だから、光
の帝国に属さない魔法使いを確保する上で、メイソンの救いの声は願ってもないものだっただろう。
「つまり、光の帝国ではなく、ゴルゴンダに学徒を兵士として渡すのか。」
「他に方法はないのだよ。この塔の魔術師は帝国から堕ちてきた者達がほとんどだ。君が言うように
帝国にとっては、自分達の脅威となるものは片づけてしまいたいに違いない。それに対抗する術は、
もうほとんど残っていないだろう。」
「だが、ゴルゴンダ軍を味方につける事が、最善とは思えないけれどね。」
これ以上は何を口にしても意味がないと思ったのか、クローアの声は徐々にけだるげなものに変化
していっている。指先で髪を弄び、酷くつまらなさそうにも見えた。
だが、メイソンとしてはそれで話を終わらせるわけにはいかないのだろう。何せ、夢の鍵が一つ開
かれてしまったのだ。しかも、塔の試験の所為で。それなりの対応を練らねばならないといったとこ
ろだろうか。
「クローア。君には、ゴルゴンダへ行って貰いたい。」
唐突過ぎるメイソンの言葉に、クローアは今度は表情を変える事はしなかった。
代わりに、ちらりとゼイクとラシルを見やり、揶揄するように首を竦めた。やはり、これ以上の話
には興味がなかったのだろう。
「そんな事よりも、この二人をどうにかしてやったらどうだ?試験の事もあるだろう?お前の考えた
試験に振り回された挙句、一方は夢の鍵を外してしまう片棒を担いでしまったんだから。」
なんらかの対応をしてやるべきでは?
女の声に、メイソンはようやく二人をまともに見据えた。千里眼であるメイソンは、きっとゼイク
が夢の鍵を解いてしまう以外の事については、全て把握していただろう。だから二人の身に危険が迫
るとは考えていなかっただろうし、仮に迫ってもメイソンが視ている以上、その時点で試験は中止に
なったはずだ。
だから、きっと試験結果は普通に下されるはずだ。ゼイクには、夢の鍵を解いたというペナルティ
がつくかもしれないが。
メイソンの眼に見つめられて身を固くした低級魔術師に、しかしメイソンは思いもかけない事を言
った。
「いいや……今から話す事はこの二人にも関係する事だ。何せ、試験は正当には成されなかったのだ
からね。だから、彼らには改めて試験を受けて貰う。」
クローアの形の良い眉が、くっと引き上げられた。ゼイクも、何、と腹の底で問いかける。ラシル
は、何も言わない。
「夢の鍵が解けた。これは確かに由々しき事態だ。だが、何よりも気になるのは、如何に親和性が高
いとはいえ、低級魔術師の稲妻程度で夢の鍵が解けるとは思えない。」
「……どこかに綻びがあるかもしれない、と?」
クローアの疑問に、メイソンは頷いた。
「その通りだ。これについて、我々だけで議論していても仕方がない。ならば此処は、ゴルゴンダ国
大統領であるヘーゲルを頼るべきだ。」
同じく、夢の鍵を持つ、ヘーゲル大統領を。
その台詞に、クローアは、静かに瞬きを一つ零した。
「なるほど、あの男、そこまで昇進したのか。」
「ああ、君が眠っている間にね。君も彼とは面識があるだろう。帝国の夢の鍵保持者である先代女帝
は身罷り、アルンハイム公も亡き今、頼るべきはヘーゲルだろう。ヘーゲルはゴルゴンダ州にある大
統領府にいるはずだ。」
「言いたい事は理解した。だが、それと此処にいる学徒二人の試験と何が関係ある?」
ゼイクは、クローアの台詞に全身全霊を込めて頷いた。
正直なところ、ゼイクには彼らの会話は異次元のものだった。二十三年前の戦争の事は知っていた
が、それに関して自分が僅かなりとも接触している事が既に夢物語だ。ゼイクとしては、試験なんぞ
落第で良いから、普通の日常に戻りたかった。今すぐに、荷物をまとめて両親のいる田園に帰っても
良い。
しかし、ゼイクの願いなど、千里眼メイソンは欠片も聞き入れなかった。
「二人には、君をゴルゴンダへと連れて行ってもらう。」
きっぱりとした台詞に、まあ、とラシルが声を上げた。その声に微かに喜びのようなものが混じっ
ている事が、ゼイクには腹立たしかった。
「勿論、その他にこの塔に駐留しているゴルゴンダ軍人も付けよう。おそらく、危険な旅になるだろ
うからな。」
「危険な旅、に、学徒二人を連れだすつもりか?」
呆れたようなものの混じるクローアの声に、メイソンはそれが冗談ではないのだというふうに頷い
た。
「それくらいの事をしなければ、上級魔術師にはなれない。魔術師は本来ならば、自ら旅立ち、そし
て研鑽を積むべきだ。……そう言っていたのは君だろう?」
「良く覚えているな……ずいぶん昔の話だ。」
決して懐かしんでいるわけではないようなクローアの言葉だが、しかし彼女はちらりとゼイクとラ
シルを見て、ゆっくりと頷いた。
「良いだろう。好きにしろ。お前が今の魔術師が生温いと言うなら、それは正しいんだろう。そして
それを正すも維持するのも、この塔の設立者であるお前の勝手だ。」
それに、お前の言う事も強ち間違ってはいない。
この試練に対してこんなはずじゃなかったと叫ぶゼイクも、この試練を喜ぶラシルも。幻視者クロ
ーアの眼には、きっと、魔術師としては映っていない。
そんな声が聞こえたような気がした。