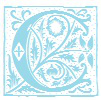
初めて入る象牙の塔の地下は、地下室らしく非常に湿っぽかった。黴の臭いはしないものの、身体
に纏わりつく湿気が身体に良いとは、とてもではないが思えない。
「きっと、生命反応そのものを制御しているんだわ。」
地下室の暗がりに灯されたラシルのそばかすが、当然のようにそう告げた。
「黴なんかの菌は、魔術師にとっては大敵だもの。古書、杖……それら全ては、基本的に微生物には
弱いものだもの。ある程度の湿気は、魔石にとっては良いから、こういう湿度にしてるんでしょうけ
ど。」
湿気が魔石に良いだなんて、初めて聞いた。何故、とも思ったが、ラシルに聞いた瞬間馬鹿にされ
る事は眼に見えているので、ゼイクは特に反応を示さなかった。代わりに、心身ともに圧迫するよう
な石造りの地下回廊の先を見据える。
一つの灯りさえ入っていない地下回廊を照らすのは、ゼイクとラシルがそれぞれ魔法で灯した、杖
の先の炎だけだ。弱々しいゼイクの炎と、煌々と光るラシルの炎だけが、闇に閉ざされている回廊の
中、ふらふらと揺れている。
試験には、杖以外の物を持ち込む事を禁止されていた。
それは、確かにこれまでの低級の試験ならば納得できただろうが、上級に昇級する際の、いわば実
践に近い状態においてはどうかとも思う。
象牙の塔の地下回廊なので勿論滅多な事は起こらないだろう、というのが理由かもしれないが、け
れども実践紛いの試験ならば、やはりある程度の準備というものを許してほしかった。灯り一つ、薬
草一つ持たせて貰えないにも拘らず、一寸先は闇の迷宮に放り込まれるのは、平々凡々なゼイクには
少々受け入れ難かった。
それとも、優秀な魔術師ともなれば、そんな事は気にしないのだろうか。
ゼイクは今現在、一番近くにいる優秀な魔術師の顔を、ちらりと横目で見る。黒縁眼鏡をかけたそ
ばかすだらけのラシルの横顔。その顔には微かな緊張こそあるものの、恐れはない。勿論、ゼイクと
て恐れているわけではないのだけれど、ただ、優等生にもなれば不平不満も零さないものらしい。
そう腹の底で思ったゼイクの耳に、小さな舌打ちが聞こえた。
「こんな暗がりで、一体どんな試験を行おうと言うの?まさか本当に、暗がりの中を延々と歩いて、
鍵の模造品を取ってくるだけじゃないでしょうね。」
ラシルが、小さく呻くように呟いたのだ。
別に、ラシルも不満を抱いていないわけではなかったらしい。尤もそれは、ゼイクとは毛色の違う
ものではあったが、しかし暗い回廊を延々と歩かされているという事実についてはゼイクも同じく不
満だった。勿論、隣を歩いているのがラシルである、という事実に関しても。それはきっと、ラシル
も同じである事だろう。
「模造品を取って来るだけなんて……仮にも上級への昇級試験なんだから、そんな事あるはずがない
わ。きっと、この回廊には何かの仕掛けが隠されているはずよ……。それが、試験になるんだわ。そ
れとも、模造品自体に何か特殊な仕掛けがあるのかしら。何せ、メイソン魔術師自らが作った物なん
だもの。魔力だって込められてるはず……。」
ぶつぶつと、ラシルの声だけが回廊の闇に響く。小さくても闇と湿気の所為か、その声は異常に大
きく反響しているように思えた。その声の所為で、何かの仕掛けの音がしても聞こえないんじゃない
かと思うほどに。
それに、ラシルの考えている事は、ゼイクも考えていた。鍵の場所に至るまでに起こる試練や、も
しくは鍵自体に込められた意図。そんな事は、きっとこれまでに試験を受けた誰もが考えた事だろう。
だが、ゼイクは思うのだ。
もしも、所謂試練のような試験であるのならば、何らかの形でそれの対応策――問題集のようなも
のが、こっそりと出回っているべきなのではないか、と。例え箝口令を敷いたとしても、学徒の間で
はひっそりと広まり、対応策が出るはずだ。
それがないという事は、まさか試験の記憶自体を消されているのか。それとも、他に何か理由でも
あるのか。
そもそも、象牙の塔の象徴である鍵の模造品を取りに行くというのは、まだ納得できる。象牙の塔
は魔術師の象徴でもあり、故に象牙の塔設立者であるメイソンの持つ『夢の鍵』が、象徴となる事も。
だが、その模造品をメイソン自らが作り上げるというのが、良く分からない。
たかだか――と言ってしまうのもあれだが――試験の為に、二十三年前の大戦の英雄の一であるメ
イソンの手を煩わせる必要があるのか。やはり、鍵の模造品にも何らかの意味があるのではないのか。
それは試験の仕掛けとしての必要性なのか、もしくはもっと別の仕掛けの為のものなのか、ゼイクに
は想像出来なかったが。
だが、ゼイクがそんな事を考え、ラシルが予断なく暗闇の中に眼を凝らしているうちに、とうとう
彼らの足取りは回廊の最深部にまで到達してしまった。
最深部に到達する前にあった長い螺旋階段は、確かに滑りやすかったが、けれども試練と言うほど
ではない。
あまりにも呆気なく、そして微かに予想していた通り何事もなく、最後の扉の前に立ってしまう事
になったゼイクとラシルは、一瞬、扉の前で狼狽えたように立ち止まってしまった。
目の前にある扉は重々しいが至って普通の鉄の扉で、背後にある闇からも何かが追跡してくる気配
はない。
全くの異常がないまま、此処まで来てしまったのだ。強いて言うならば、何事も起こらないという
この状況こそが異常だった。
その異常について声に出す事を辛うじて飲み込んで、ゼイクは鉄の扉に手をかけた。長い間、闇と
湿気の中にあった所為か、鉄の取っ手は酷く冷え切っていた。海底に沈んでいたかのようなそれを掴
んで、思い切り押し開けば、想像していた抵抗は全くなく、その所為でゼイクは転がるようにして最
深部の部屋に入るような形となってしまった。
ラシルも、あまりにも呆気なく最後の扉が開いてしまい、眼を丸くしているようだった。
「どういう事、これは?」
何一つとして仕掛けもないままに、部屋の中央にある小箱が、薄らと輝いているのを見つけたのだ。
その輝きの源は、銀色の鍵だった。
「此処から、何か仕掛けがあるという事?確かに、あの鍵からは何らかの魔力を感じられるけど……。」
口ごもるラシルも、戸惑っているのだ。優等生として試練に挑もうとしていたのに、こんなふうに
呆気なくては戸惑いもするだろう。勿論、まだこれで終わりと決まったわけではないのだが。
ゆっくりと鍵の入っている小箱に近づき見下ろせば、やはりそこには、さあどうぞと言わんばかり
に銀色の鍵が煌めいていた。もしもこれで試験が終わりならば、さぞかしこの瞬間に、幾多の魔術士
を悩ませてきたに違いない。
「罠や、魔法の仕掛けは見当たらないわ……。」
ラシルはくすんだ金髪を揺らして周囲を探った後、普段の優等生然とした自信ありげな灰色の眼差
しを更に当惑させた。
「鍵そのものにも、何か仕掛けのあるようなものは感じないし……。本当にこれで終わりなのかしら。」
そう呟いて鍵に手を伸ばそうとするラシルの手首で、バックルで留められた紫色の魔石が煌めいた。
その煌めきを見て、ゼイクはラシルの今にも鍵を取ろうとする手を掴んだ。
「何するの?!」
きっと、ゼイクのような平凡な魔術師に、行動を遮られた事が嫌だったのだろう。だが、今すぐに
その鍵に手を触れるのは軽率だと思ったのだ。この試験についての情報は驚くほど少ない。
しかし一つだけ聞いていた事があったではないか。
己の魔石に、選定されるのだと。
ならば此処で頼るべきは、おそらくは己の知識や技量ではなく、魔石に問うべきではないのか。
ゼイクの魔石は何も答えない。ラシルの魔石は薄く煌めいている。どちらも、まだ答えを告げるつ
もりはないような素振りだった。
だが、魔石云々よりも気になる事が。
「……これ、本物の鍵か?」
「何言ってるの。模造品に決まってるじゃない。」
「そうじゃない。本当に鍵を模造したものなのか。取ってくるべき鍵は、本当にこれなのか。」
そう、二人共、鍵の形を教えてもらっていない。それどころか、この学園の象徴が鍵であると教え
られていても、鍵の形までは教えてもらっていない。アルゴンヌ海を封じた『夢の鍵』の形は、誰も
知らない。
六つの鍵がかけられ、そして更に四つの鍵が施され、最後に再び四つの鍵によって閉ざされた。
それ以外の事は、何も知らないのだ。
「鍵だ鍵だと言うから、俺達は普通の鍵を想像していたけど、良く考えたら現物を俺達は知らないぞ。」
「じゃあ、これは偽物だって事?私達が意気揚々と持って帰ったら、即座に落第させる為の。」
ラシルは、まるで炎で炙られた鉄にでも触ったかのように手を引っ込めた。小箱の中の鍵は、相変
わらず淡い光を放っている。
「でも、それじゃあ本物は何処?」
「分からないけど、けど……。」
次の瞬間、ゼイクは絶句した。それは、ラシルも同じだった。
二人の間に挟まれて淡い光を放っていた鍵が、手を伸ばされない事に不満でも感じたのか、突如と
して輝きを増すなり、滔々と光を吐き出し始めたのだ。溢れ出す光は、しかし何処かに流れ去る事は
なく、その場に蟠り続けている。
上塗りされていき、明らかに肥大していく光に、ゼイクは咄嗟に飛び退った。一拍遅れて、ラシル
も。
直後、二人がいた場所を鱗だらけの棘のついた巨大な尾が薙ぎ払った。
眼前を通り過ぎた凶悪な固い尾に、ゼイクはますます言葉を失った。ようやく拭い去られようとし
ている光の隙間から、しゅうしゅうと聞こえる音は、明らかに巨大生物の呼気であった。
「竜?!そんな!」
全容が明らかになったその姿に、ラシルは戸惑いや驚愕、その他諸々の入り混じった悲鳴を上げた。
ゼイクも、悲鳴を上げたい気持ちだった。
光を突き破って目の前に広がった鱗に覆われた生物は、最初に感じた巨大というほどの大きさでは
なかったものの、しかしそれでも、ゼイクやラシルが見上げるほどの、一つの納屋ほどの大きさであ
った。それに、いくら小さ目と雖も、竜は竜だ。半人前の魔術師が手を出せる相手ではない。
「こんなのが、試験ですって?!ふざけてるわ!」
同感だ。
だが、試験地の最深部で、明らかに竜はのたうっている。何かの手違いならば、この塔の魔術師の
程度が知れるというものだ。しかし、今そんな文句を言っていても仕方がない。ゼイクは身を翻して、
さっき入ったばかりの鉄の扉に飛びついた。
が、案の定というかお約束というか、そこはぴたりと閉ざされて、動く気配はしなかった。そんな、
という悲鳴がラシルから聞こえたが、それに構う余裕はない。ゼイクは腕に取り付けている魔石を、
頼るように少し押さえた後、掌に向かって稲妻を思い描いた。そして、腕を突き出す。
稲光。
爆ぜるような音と共に掌から走り出した稲妻は、時折折れ曲がりながら、それでも鉄の扉に果敢に
も飛びかかって行った。
だが、その光は鉄の扉に吸い込まれてしまう。まるで、何もなかったかのように。音一つ、しない。
その光景に眼を見開いている暇もなかった。背後に迫っていた竜が、後脚だけで半ば立ち上がり、
その鋭い鉤爪を振り下ろそうとしていたのだ。
咄嗟に飛び退るのと、竜の横っ面に尖った氷柱がぶつかって砕けるのは同時だった。ラシルも魔法
を使用し、竜に攻撃を仕掛けたらしい。だが、竜の外殻は硬く、傷をつける事はおろか、よろけさえ
もしなかった。
勝てるわけがない。
未熟な魔術師の魔法になど、びくともしない竜を見上げて、ゼイクは腹が立ってきた。こんな無茶
な試験を受けるくらいなら、本当にさっさと田舎にすっこんでいればよかった。試験に落ちてから、
なんて先延ばしにする必要なんてなかったのだ。
視界の隅で、ラシルが必死になって杖を振り上げて魔石を発動させている姿を見つけ、ラシルでも
無理だろうな、と思う。如何に象牙の塔きっての才媛であっても、所詮は低級魔術師である以上、今
まで竜と戦った事なんてなく、故に竜に対して何が有効か分からないのだ。書物の上の知識はあって
も。
そしてそれはゼイクも同じ事。
竜になど、対峙した事などない。
それでも、やらねばならないのだ。この試験は。如何に理不尽であろうとも、それが低級から上級
に昇級するという事だろう。それが出来なければ、落ちるだけだ。そういうふうにして、延々となさ
れてきたのだろう。
だとすれば、きっと死ぬ事はない。それだけが、この非常事態において唯一の救いだった。
ちらりと、もしかしたら手違いなのでは、という思いも過ったが、その考えはあまりにも愉快では
なく、頭から打ち払う以外になかった。
気炎を上げている竜に、ゼイクはもはや苦笑いを浮かべるしかないまま、向き直る。炎を口から吹
き上げている竜の肩越しには、氷柱ではなく冷気を噴き上げて竜に噴射しようとしているラシルがい
た。確かに、竜は冷気に弱いようだという話も聞いたような気がするし、目の前にいる竜はどちらか
と言えば炎を好んでいるようではあるが、しかし実際の所、竜というものは特別何かが苦手であると
は定まっていないのだ。炎ではなく冷気を好む竜も、伝説では数多くいる。
確かに赤い鱗は炎を示しているような気もした。だが、氷柱にはびくともしなかった。それに冷気
攻撃はラシルが行うというならば、ゼイクは他の魔法を試すべきだろう。
思うや否や、ゼイクは左腕に取り付けた魔石に右手を翳すと、扉に目掛けて撃った雷を右手に生み
出し、竜に放った。
火花を撒き散らしたそれを、竜は首の一振りで打ち払う。弾け飛んだ雷は、別々の所に霧散して、
暗い部屋の隅や床の上で小さく踊った。
やはり効果はないか。
何食わぬ顔で唸る竜を眺めて、ゼイクは失笑した。当たり前と言えば当たり前だ。ラシルの攻撃が
聞かなくて、ゼイクの攻撃が効く事自体、弱点云々以前に二人の技量を考えればおかしい話だ。
だが、とゼイクは妙な気分になった。自分の考えに、ではない。さっき稲妻を撃った瞬間に、何か
妙だったのだ。皮膚や神経、そして視覚が、飛んだような気がした。
見ている景色に、一瞬だけ別の何かが紛れ込んだかのような、そんな違和感が。
その違和感の原因を確かめるよりも先に、竜が大口を開いて、口に並んだ牙を見せつけるようにゼ
イクに突進してきたのだ。咄嗟に、未だに魔石に留まり続ける雷鳴を撃ち落した。むろん、竜には何
の牽制にもならなかったが。
ただ、ぽっかりと開く竜の大口。それが、雷鳴と共に、確かに一瞬消え去って、竜の後ろで悲鳴を
上げているラシルの姿が見えたのだ。
何、と、その一瞬の間にゼイクは自問した。竜が雷鳴によって消えたその理由は一体何か、と。例
えば、暗闇の中の稲光によって、その僅かの間だけ周囲が照らされるように、齎された、それは。
自問が終わるのと同時に、竜の大口は、ゼイクの頭を躊躇いなく噛み砕いた。
瞬間、竜の姿は跡形もなく消え去った。立ち竦んだゼイクが見ているのは、竜の暗く赤い口腔では
なく、悲鳴を上げる姿で凍り付いているそばかすだらけのラシルだった。消え去った竜の身体越しに
見つめ合った二人は、唖然として口をきく事も出来ない。口から、短い呼気を吐き出すだけだ。
けれども我に返ってみれば、竜の炎以外には灯りのなかった部屋が、何故か隅々まで見渡せるほど
の明るさを保っている事に気が付いたはずだった。それは、確かにこの部屋に何らかの力が行き渡っ
た証拠だ。その証拠を裏付けるように、冷たく、そして闇の所為で明瞭ではなかった壁が緩やかに動
いて、ゆったりとした足音を近づけさせていた。
「さっきから、鍵を開こうとしていたのは、誰?此処はメイソンによって管理されていると思ってい
たんだけれど、眠っている間にこの塔の体制が変わったのか?」