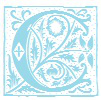 一章:象牙の塔
一章:象牙の塔
軍事国家ゴルゴンダは、大統領を国家元首とする。大統領は『世界の血』によって生み出された
『人の子』の意志を継ぐ者とされており、代々後継者は大統領によって、『人の子』の意志を継ぐに
相応しい者が選任される。
『人の子』。
世界を造り給いし『世界の血』が、一番最後に作り上げた種族だと、伝承上はそうなっている。
『世界の血』は、最初に海人を造り、そして川人、巨人を造ったと。しかし彼らは争いを繰り返し、
その性質に『世界の血』は失望した。故に、彼らを統べる存在として『人の子』を創り上げた、と。
此処までは、ゴルゴンダ国に伝わる伝承も光の帝国に伝わる伝承も同じだ。
ただ、その後の解釈は、この二国間で全く違う。『世界の血』を濃く受け継いだと謳う光の帝国で
は、『人の子』もまた、他の種族と同様に『世界の血』を失望させたのだと。
しかし『人の子』が自分達の国を造ったと謳うゴルゴンダでは、『人の子』の力を恐れた『世界の
血』が『人の子』を滅ぼそうとしたのだと。
異なる伝承を信じる二国は、『世界の血』の背骨と言われるアルンハイム山脈を境に、自らの主権
を主張し、今日まで小競り合いを続けているのだ。
光の帝国は魔法を、ゴルゴンダは機械の力を用いて。
だが、機械産業が主であるゴルゴンダにも、魔術師はいる。ゴルゴンダの南東部ダマスカス州にあ
る孤島。沖合に遠く見えるその島は周囲を絶壁で囲まれており、切り立つ様な崖の上に、細く高い塔
がそそり立っていた。
象牙の塔。
人々にそう呼ばれる塔は、ゴルゴンダの中で唯一魔術師が集う場所だ。ゴルゴンダには決して生ま
れる事のない魔術師達が、何故そこにいるのかと言われれば、光の帝国から逃げてきたから、もしく
はゴルゴンダに奴隷として連れてこられた光の帝国の民が、自由を求めて集ったのだ。
しかし、単純に逃亡者だけが作り上げた塔でしかないのなら、すぐさま外圧に負けて崩れ去ってし
まっただろう。それが成されなかったのは、単に象牙の塔の設立者が、二十年前の白の集団との争い
で指揮官の一人として立ち上がった、メイソン・アーガスであったからに他ならない。
もともと、魔術師達に魔法の正しい知識を教えるべきと唱えてきたメイソンは、学舎としてこの塔
を造ったのだ。それが、駆け込み寺のようになってしまったのは、この世界の歪の所為に他ならない。
尤も、魔術の正しい知識が必要なのは、正に奴隷や逃亡してきたから魔法の事を良く知らない光の帝
国の民なのだから、メイソンの提唱してきた理想からかけ離れてしまったわけではないのだが。
だが、流石に奴隷や逃亡者を多く囲っているという事実を、ゴルゴンダ政府が黙っているわけには
いかなかった。先の戦いで指揮をとったのは、何もメイソンだけではない。ゴルゴンダ国大統領ゴー
ルドン・マーカーも同じく指揮官だったのだ。
ゴールドンはメイソンに象牙の塔の運用を許可した。光の帝国からの干渉もゴルゴンダ政府が対処
しようと。ただし、その代わりに象牙の塔にゴルゴンダ軍を逗留させるように告げたのだ。万一、魔
術師達が反乱を起こした時の為に。
そしてメイソンはこれを承諾した。
かくして、機械産業の発達したゴルゴンダ国は、唯一手にする事の出来なかった魔法の力も、間接
的にではあるが手に入れたのだ。
そこには魔術師を軍に編集するつもりだとか、そういう思惑があるのではないかという噂が飛び交
ったが、どれも真実味を帯びた噂の域を出ないものであったし、そんな思惑をよそに、象牙の塔にや
ってくる光の帝国の国民だった者の数は増える一方だった。
しかし、象牙の塔は学舎である。象牙の塔に入ってきた以上、魔術に対する知識を学ばなければな
らないし、塔に居続けようと思うならばそれなりの功績を残さねばならない。それ故、講義もあれば、
むろん試験もある。
試験は一年に一回、進級試験がある。魔術師には、明確にクラスが存在している。他の人々は魔術
師は魔術師でしかないだろうが、魔術師という言葉自体も実はクラスの一つなのだ。
見習い、魔道士、魔法士、魔術士、魔術師、魔法師、魔導師と七つのクラスに分けられている。魔
術士までは、低級だ。師という言葉がついてからようやく上級となる。魔術士までは、ある程度の努
力でなんとかなる部分があるが、そこから上級に上がろうとすると、知識や努力だけではどうにもな
らないところがあるのが事実だ。
故に、今年遂に魔術師の試験を受ける事になったゼイク・ルアーンは重苦しい溜め息を吐くしかな
かった。
ゼイクは象牙の塔にやってきて今年で四年目になる。父親と母親は光の帝国からの難民で、今はゴ
ルゴンダの北部で農家の手伝いをしている。何故難民となったのかはゼイクは良く知らないが、どう
やら光の帝国とゴルゴンダの国境にあるアルンハイム領にて領王の暗殺騒ぎがあって、そのごたごた
でゴルゴンダに行くしかなかったのだという。
ゴルゴンダでの扱いは、決して悪くないと思う。偶々行き着いた北部が田園地帯であり、人々も穏
やかな人が多かった為か、両親も幸せそうだ。ただ、魔術関係の物は全て帝国に置いてきてしまった
ので、ゼイクに魔法を深く教える事はできなかった。だからゼイクは象牙の塔にやってきたのだ。
別に来なくても良かったのに、とゼイクはいつも思う。
ゼイクは確かに此処までは一度も試験を落とす事なく進級してきた。だが、試験の結果は完全に平
凡なものだ。格別悪いわけではない。だが、特別秀でているわけでもない。それはある程度勉強して
いる者ならこれぐらいは出来るだろう、というレベルのものだ。そしてセイグは、それが自分の能力
の限界であると気づいている。
きっと、自分は上級魔術師にはなれないだろう。
それで良いと思う。それを目途に象牙の塔を去り、両親の元に戻り、一緒に農家の手伝いをすれば
良い。そう思い、試験の説明を教官から上の空で聞いていたのだが。
魔術師昇級試験は、二人一組で行われるものであるらしかった。二人で象牙の塔の地下――此処は、
上級魔術師にならなければ自由に出入りする事は出来ない――へ潜り、地下にある象牙の塔の象徴と
もいえる鍵を取ってくるというものだ。
象牙の塔の象徴たる鍵とは、『夢の鍵』の事である。
二十年前、アルゴンヌ海に沈め、封印した白の集団が眠る場所。その場所は、現実よりも夢に近い
場所であり、六つの鍵に更に四つの鍵を施し、更に四つの鍵によって閉ざされている。夢に近い場所
であるが故に、封印を施した鍵の事を『夢の鍵』と呼び、その内の一つを、象牙の塔の筆頭であるメ
イソンは所有しているのだ。
試験は、その鍵の模造品を取ってくる事。流石に、本物を手渡すわけにはいかないのだろう。それ
でも、メイソン自らが作るというその鍵は、模造品と雖もそれなりの魔力を帯びている事は間違いが
なかった。
本気で上級魔術師になろうと考えている者にとっては、やはりそれなりの憧れがある品だろう。ゼイ
クには、全く憧れは抱けないが。
苦笑するゼイクは、勿論自分がその鍵を取って帰ってこれるとは思っていない。
だが、教官の吐き出した言葉に耳を疑った。
「ゼイク・ルアーンは、ラシル・ハワードと組むように。」
ぎょっとするゼイクの耳に、はい、と歯切れの良い女生徒の声が響いた。視界の端にも頬を微かに
紅潮させた女生徒が見える。
まさか、とゼイクは狼狽えた。
まさかこの自分が、よりにもよってラシル・ハワードと組んで、試験を受けるだと?
ゼイクは咄嗟に何かを言わなくてはと思い教官を見たが、教官は既に別の魔術師達の組み合わせを読
み上げる事に移ってしまっている。仮に教官がゼイクの言葉を聞いたとしても、聞き入れてくれるわ
けがない。一度決まった事が覆るという事は、非常に少ないのだ。
だが、しかし。
ゼイクはちらりと、自分と組む事になった女生徒を視線だけ動かして見やる。くすんだ金髪の下に
ある顔を、これから訪れる更なる試練に向けて紅潮させている彼女。ラシル・ハワード。この塔きっ
ての才媛であり、ゼイクと同じく四年前に象牙の塔にやってきて、ゼイクと同じく一度も滞る事なく、
魔術士になった。
けれども、成績はゼイクとは天と地ほどの差がある。象牙の塔きっての才媛は、まさに才媛たる功
績を修めて進級しているのだ。試験は常に一位であり、低級であるにも関わらず、上級魔術師が見る
事を許された図書の閲覧を認められている。自他共に認める優等生なのだ。
そんな優等生と組まされるなど、どう考えてもゼイクはこの試験に通らねばならないと言われてい
るようなものではないか。二人一組で行われる試験とは、必ず二人同時の合格が求められる。ゼイク
が落ちれば、自然とラシルも落ちる。そしてそんな無様な事は、決してラシルは許してはくれないだ
ろう。
ラシルは才媛であると同時に、非常に誇り高い女でもあるのだ。
現に、思いもかけぬ事態に狼狽えるゼイクに、ラシルは教官が解散の言葉を放った後すぐに近寄っ
てきて、こう言い放ったのだ。
「ゼイク、私の脚を引っ張らないで頂戴ね。」
優等生が平凡な学徒に放つには、これほどまで相応しく、そして残酷な言葉はあるまい。何せゼイ
クはラシルの脚を引っ張るどころか、おそらく試験には落ちるだろうと考えていたのだから。
「この試験は二人一組――つまり、どちらか一方が合格するという事はないの。あくまでも、二人一
緒に合格しなくては意味がない。勿論、私は貴方の分を補うつもりだけれど、だからといって貴方は
何もしなくて良いというわけじゃないわ。せめて、脚を引っ張らないようにして頂戴。」
きっぱりと言い放った、そばかすだらけの顔を見つめ、ゼイクは絶句した。実際、魔術師きっての
才媛に面と向かれて言い放たれて、誰が何を言い返せようか。
口性のない輩ならば、なんとか切り返すかもしれないが、ゼイクはそんな口の回るほうではなかっ
たし、それに実際にそんな事が出来る人間は、この塔の中にはいないだろう――ラシルの魔法力を恐
れて。まあ、陰口を叩く輩はいるだろうが、それらはラシルにとっては敵ではない。
というか、ラシルにとっては誰一人として敵ではないのだ。ゼイクも含めて。きっと、同じ魔術士
の事など、ラシルは何とも思っていないに違いない。それだけラシルは一人飛び抜けている。魔法の
技術、知識、どれをとっても低級魔術師達は手も足も出ない。
その事が分かっているから、ラシルは低級魔術師を誰一人として相手にしないのだろう。一人、上
級魔術師が手に取れる禁書を持って、図書館に向かうラシルの姿を見て、ゼイクは重苦しい溜め息を
吐いた。
ラシルがゼイクに話しかけたのは、単純に自分の魔術師としての出世の脚を引っ張りそうだったか
ら、だ。でなければ、ゼイクのような中間の中間である魔術師に、話しかけようなど思いもしないだ
ろう。そしてこの先農家の手伝いをして暮らそうとしていたゼイクとしては、出来れば一生些細な事
でも話しかけて欲しくなかったというのが正直な気持ちである。
もう一度重苦しい溜め息を吐いて、のろのろとローブを引き摺って宿舎に戻ろうと脚を動かすゼイ
クの姿は、見る者に憐れみを誘う。
それは、魔術師を見張る為に駐留しているゴルゴンダ軍人も同じであったらしい。
「どうしたの、そんな溜め息を吐いて。」
背後から、金属の擦れ合う固い音に被さるように、それとは正反対の物柔らかな声が追いかけてき
た。振り返ると、日に焼けたような肌に焦げ茶の長い髪を頭の上のほうで一纏めにした女性軍人が、
笑みを湛えて立っていた。
見た目は酷く華奢そうに見えるが、ゴルゴンダ軍が使う重苦しそうな甲冑に身を包んだ彼女の腰に
は、太い剣が差しこまれていた。
「ジェザシータ。」
ゼイクは、女性軍人の顔を見て、ほっとしたような表情をようやく浮かべる事が出来た。まだ若い
が、しかし象牙の塔の駐留軍としての副官を務めるジェザシータは、軍人にありがちな横柄な態度は
なく、柔和な物腰で魔術師達の間での評判も良い。
尤も、その物腰が、逆に軍人からの反発を招く事もあるようだが。
「どうしたもこうしたもないよ。」
自分の姉のような年齢のジェザシータに、ゼイクは口を尖らせた。
「次の進級試験は二人一組でやるって言うんだけど、その相手がラシルなんだ。」
「ああ、才媛ラシル。」
ジェザシータは愉快そうな口調で言った。
「あら、だったら試験では楽できるんじゃなくて?私は魔法の事はとんと疎いけれど、ラシルがこの
塔では一、二を争う魔術師になるんじゃないかっていう噂は聞いてるわ。そんな子と一緒に試験を受
けるんなら、通ったも同然じゃないの?」
呑気なジェザシータの言葉に、ゼイクは首を振って自分の未来予想図を騙った。
「俺はこの試験に受かるつもりなんてなかったんだ。自分に魔法の才能がない事は分かってるし。そ
ろそろ田舎に引っ込んで、親の手伝いでもしようかと思ってたんだ。それなのに、ラシルなんかと組
まされちゃって。」
計画がめちゃくちゃだ、とゼイクは嘆く。その様子を、ジェザシータは明るい眼で笑って見やり、
でも、と言う。
「一応、これで受かる目途は立ったわけでしょう?」
「どうかな。確かにラシルは才媛だけど、俺の分までどうにか出来るかは分からないだろ。まあラシ
ルは補うって息巻いてたけど、同時に足を引っ張るなって釘も刺されてる。実際のところ、ラシルも
分からないんじゃないか?」
そう、試験に通るかどうかはまるで分からないのだ。
才媛、天才と謳われる魔術師だからと言って、試験に受かるという保障はまるでないのが、象牙の
塔の実状だ。低級から上級に上がるその時に、本当に天才であるか振り分けられると言っても良い。
ここで、単純に知識だけを詰め込んできた――例えばゼイクのような――輩は、確実に振り落される。
そして、本当に魔術師としての才能がある者だけが選ばれるのだ。
ラシルが知識だけの人間だとは思わない。上級魔術師のみに許されている禁書を読める事からも、
教官達もラシルは天才であると認めているのだろう。だが、その事実を本当に認めるのは教官ではな
く、魔法の側なのだという。
魔法の側、とはおかしな言葉に聞こえるかもしれない。
だが、事実そうなのだ。
ゼイクは自分の腕に括りつけられたバングルを見下ろした。そこには、緑色に光る石が煌めいてい
る。この石こそが、魔法の側――魔石だ。
魔石とは、文字通り魔力の込められた石の事だ。これを手にする事で魔術師達は自分の魔力を増幅
させたり、別の力に変換したりする事が出来るのだ。そしてこの石こそが、魔術師が魔術師たる所以。
光の帝国が、自分達こそ創造主たる『世界の血』の力を色濃く受け継いでいると主張する理由。
魔術師は、生まれながらに魔石を生み出す事が出来る人間の事なのだ。
魔術師は、必ず、生涯に必ず一つの魔石を生み出す。それは、人間の成長で言うならば、初潮を迎
える時期に一致する。子供から大人へと成長する、身体も心も不安定な時期に、魔術師は自分の分身
である魔石を生むのだ。そして生み出された魔石は、生み出した魔術師の手元で力を発揮する。
最近、ゴルゴンダでは魔石をどうにかして機械に組み込み、その力を引きずり出そうという試みが
なされているようではあるが、それらはやはり魔術師が魔法を使うのに比べると遥かに心許ないのだ
ろう。実用化されたという話は終ぞ聞かない。
しかし、それでも、実用的ではないにしても装飾品として、或いは魔術師に対する嫌がらせとして、
魔石が盗まれるという事件は絶えない。魔石を奪われて魔法が使えなくなるわけではないが、魔力を
思い通りに調整する事は出来ないのだから、魔術師にとっては大きな痛手だ。
故に、魔術師にとって魔石は、命の次に大切なものと言える。
その魔石が、低級から上級への昇級試験では、魔術師が魔術師として生きていくに値するかを定め
るのだと言う。
それが、如何なる方法によって成されるのか、ゼイクには分からない。『夢の鍵』の模造品によっ
て、魔石に何らかの力が働き、それによって選定が成されるのかもしれないが、全ては憶測に過ぎな
かった。
ただ、もしかしたら、自分の分身である魔石に、魔術師として不適格と言われたら、予想していたと
しても多少はショックかもしれないが。
「大丈夫よ。きっと上手くいくわ。」
黙り込んだゼイクに何と思ったのだろうか。ジェザシータは殊更明るい声を上げ、金属のグローブ
に包まれた手で、ゼイクの肩を軽く叩いた。軽くではあったが、ずっしりと重厚感のある手に、ゼイ
クは小さく苦笑した。
「……だと良いんだけど。」
けれどもきっと、そんなに簡単な話ではない。
ラシルの固い口調を思い出し、ゼイクはもう一度だけ、溜め息を吐いた。
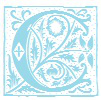 一章:象牙の塔
一章:象牙の塔